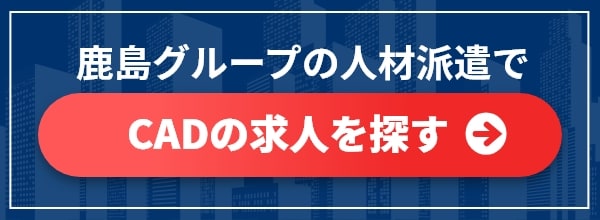日本国内における
建設業界のBIM普及状況
と主要BIMソフトウェア(2025年)
日本におけるBIMの普及状況(2025年)
普及の現状
大手ゼネコンや設計事務所ではBIMの導入が進んでおり、設計から施工、維持管理までの一貫した情報管理が実現されています。
一方で、中小企業の導入率は依然として低水準であり、導入コストや教育体制の不足が主な障壁となっています。
国土交通省は公共工事でのBIM活用を推進しており、今後は中小企業にも導入が求められる流れが強まっています。
普及率と導入状況
建設業界全体では約40%の企業がBIMを導入済みと回答しています。
そのうち、「積極的に活用できている」と答えた企業は約30%にとどまっており、導入と実運用の間にギャップがあることが分かります。
従業員100名以下の中小企業でも、約40%が「導入し、活用できている」と回答しており、クラウド型BIMやサブスクリプションモデルの普及が後押ししています。
大企業では3割以上がBIMを活用しているものの、データ管理や関係者間の調整の複雑さが課題となっています。
普及を妨げる要因
- 高額な初期投資(ソフトウェア、ハードウェア、教育費)
- 既存業務との互換性の低さ
- BIM技術者の不足
- 業務プロセスの大幅な見直しが必要
普及を後押しする要因
- 3Dモデルによる視覚的な合意形成の容易さ
- 設計・施工の効率化とコスト削減
- 国の政策支援と公共事業での義務化の動き
主なBIMソフトウェアとその特徴(2025年)
Revit(Autodesk)
建築・構造・設備を統合管理。クラウド連携が強力。ゼネコン・大手設計事務所に多く導入されています。
Archicad(Graphisoft)
直感的な操作性と高い視覚化能力が特長。設計者に人気で、建築設計事務所に広く使われています。
GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト)
日本の建築基準法に対応しており、中小企業や地方の設計事務所・工務店に適しています。
Vectorworks(Vectorworks社)
汎用性が高く、建築のみならずインテリアやランドスケープにも対応。デザイン事務所に多く採用されています。
Rebro(NYKシステムズ)
設備設計に特化した国産BIMソフトで、操作性が高く国内での導入実績も豊富です。