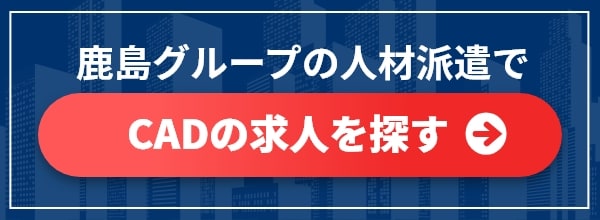設計職のキャリアを考える:
建築設計事務所とゼネコンの違い
建築設計に携わる2つの道
建築設計に関わるキャリアには、「建築設計事務所の設計職」と「ゼネコン(総合建設会社)の設計職」が存在します。一見すると同じ“設計職”という名称ではありますが、実際には業務の性質や関わるプロジェクトの規模、キャリアの描き方に大きな違いがあります。本記事では、それぞれの働き方や適性について解説していきます。
建築設計事務所で働くという選択
建築設計事務所での設計職は、主に意匠設計(いわゆる建築デザイン)に携わることが多く、自らの建築観や美意識を存分に発揮できる環境です。クライアントとの打ち合わせから建築コンセプトの立案、基本設計・実施設計、プレゼン資料の作成、行政との協議や確認申請、さらに現場監理まで、一連の業務を広く担当します。小規模から中規模の設計事務所では特に、建築家個人の個性が色濃く出る傾向があり、公共建築やコンペティション案件に関わる機会も豊富です。
このような設計事務所の設計職には、空間表現やデザインに強い関心があり、自分の建築観を深めたいという志向の方が向いています。また、将来的に独立を視野に入れている方にとっても、現場全体を主導できる環境は非常に有意義なキャリアパスとなるでしょう。
ゼネコン設計職の現実的な視点
一方、ゼネコンの設計部に所属する設計職は、施工を前提とした実施設計や施工図の作成を中心に行います。対象となるのは、病院や商業施設、超高層ビルといった大規模プロジェクトであることが多く、現実的な制約(施工性・コスト・工期など)を踏まえた設計が求められます。加えて、構造・設備・施工部門など社内の多様な専門チームと連携しながら設計を進める必要があり、発注者や設計事務所との協議、VE(バリューエンジニアリング)提案、設計変更への対応といった調整業務も多く発生します。
ゼネコンでの設計職には、論理的な思考力や社内外との調整能力が求められます。技術力と同時に、現場とのスムーズな連携ができる実務力を発揮できる人にとって、安定した企業内でのキャリア構築が可能です。
自分に合った設計職を見極める
このように、設計職と一口に言っても、働く場所や関わる業務によって求められるスキルや適性には大きな違いがあります。意匠や表現を追求する設計事務所の仕事と、実務・施工面での完成度を追求するゼネコンの設計職。それぞれの特徴を理解し、自分がどのような建築に携わりたいのかを見極めることが、キャリア選択の第一歩となります。
また、最近では設計職を目指す前段階として、「CADオペレーター」という職種を選ぶ人も増えています。CADオペレーターは、図面作成の実務を通じて設計スキルの基礎を身につけることができ、設計者としての視野を広げる貴重な経験になります。CADオペレーターとしての経験は、将来的に設計職へとステップアップするための強固な足がかりとなるでしょう。